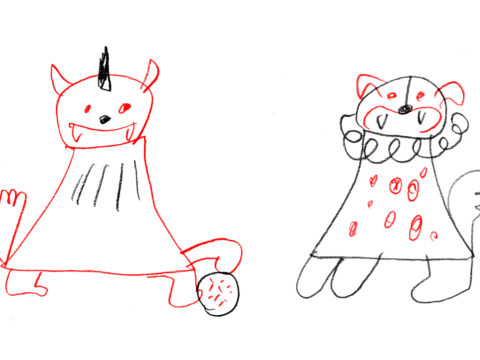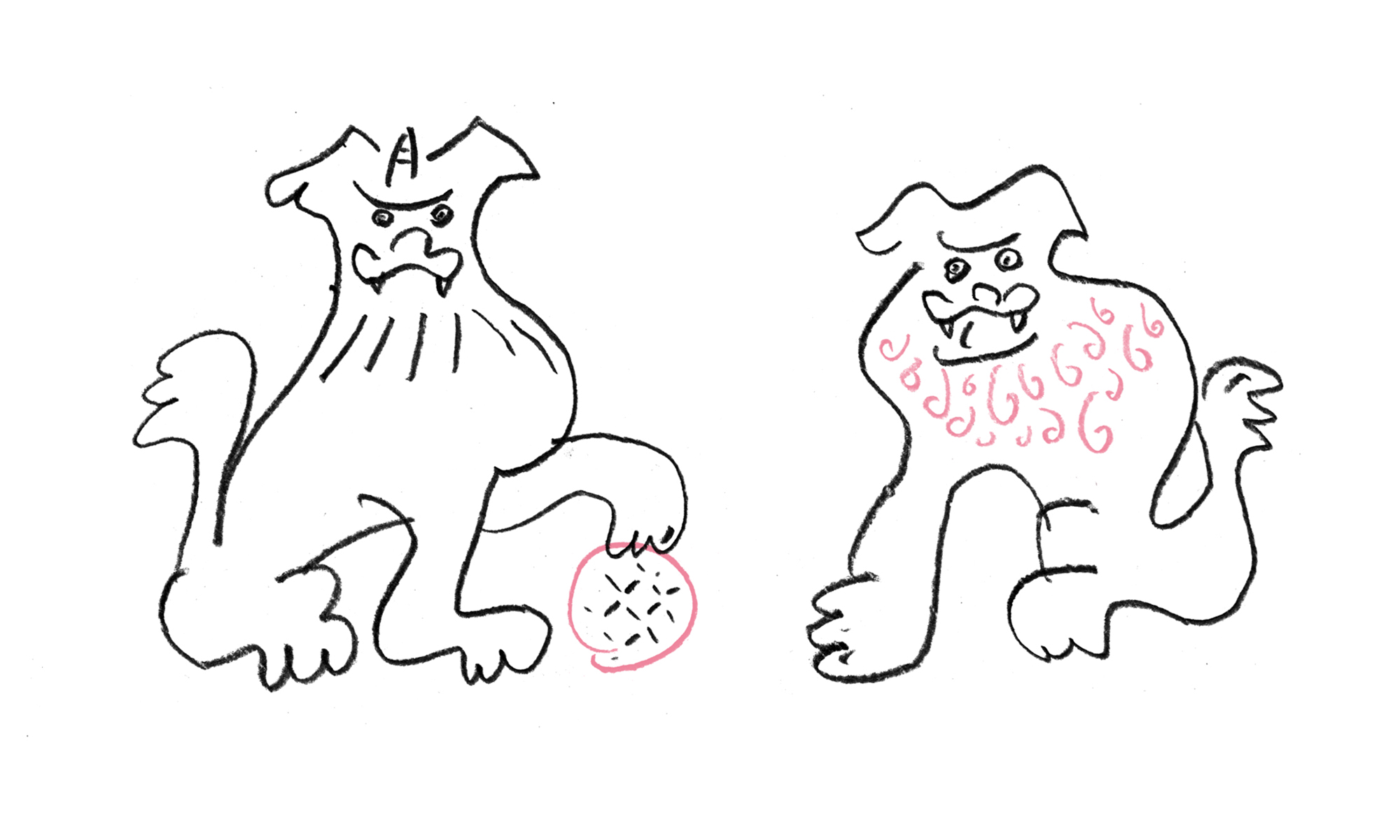
「社長やって」と言われて、“他人”の会社を引き受けた理由。会計室は「基点」をつくる(代表メッセージ・五藤 真)
こんにちは。2025年9月から、株式会社きてんの共同代表になった五藤真です。
創業者の中田さんから「会社の共同代表と社長をやってくれない?」と言われて、おっけー、と答えたので、共同代表になりました。とはいえ、以前設立した株式会社を一度解散したときから、税理士資格をとった後はてっきりまた自分で会社をつくるもんだと思っていました。自分でもなんで気軽に引き受けたのだろう?と思いつつ、経緯や、これからのことをみなさんにお伝えできたらと思います。
そんなに違和感を覚えずに中田さんの「一緒に会社をやろう」に返事ができたのは、聞いたときに面白そうだと思ったから、そしてそれまでの過程で中田さんのことを信頼していたからです。それぞれ書いてみようと思います。
他人の靴を履く面白さ
もともと僕がやっていたcountroomという会社(2018年創業〜2022年解散)には、主体的にcountroomのメンバーでいてくれる頼もしい仲間がいました。一方で、最初会社を作ろうと決めたのも、最後解散すると決めたのも僕で、最終的には全て僕の判断に委ねられていました。会社の社名も(当初案は創業時メンバーに即却下されましたが笑)、コンセプトも、全て当時の自分の生き方を反映したもので、自分の分身のようなものでした。
さてそれでまた新しい法人をつくるとなると、次はどういう方針で、どういう社名にしようかと思いあぐねてもいました。といったところで、他人の会社の共同代表になる(!)という選択肢に風通しの良さを感じました。自分だけでは見えない景色が見えそうだな、面白そうって、わくわくしたんです。「私は会社に残るしこれまで以上にやりたいことをやるしきてんで積み上げてきた文化もカラーも踏襲するけど、共同代表として社長はやってよ」なんてぶっとんだことを言われることは今後もうないでしょう。どういうこと? やってみよ。
立ち止まれること、戻れること
そうは言っても他人の会社を引き受けるのは、中田さんに対しても、また中田さんの事業関係者に対しても責任を伴いますし、重たいです。それでもできると思ったのは、悩んだら話し合えるだろうという信頼があったからです。行き詰まりを感じたり、または相手が何か危ういと感じた時に、ちゃんと話して、大事にしたいことに立ち戻り、軌道修正ができそうだと思ったからです。
二人の性格はまあまあ違うのですが、相手が話していたらそれを一回受け止めてみる。そういう姿勢は持てるんじゃないか、それでひとまずはいいんじゃないか。お互いにこれからも、この姿勢を大事にしていこうと思っています。
二人だけの会社ではない
法人は手段としてのただのハコに過ぎないと思う一方で、どこか、自分(たち)とは切り離された分身であるという感覚もあります。実際、前に会社をやっていたとき、自分の身を離れて会社が他人に語られていったことを覚えています。
中田さんと新体制準備を模索しながら、「きてんの文化を作っていきたいね」という話をしていました。行動指針として ”Social”“ Alternative” “Empowerment” という言葉を置いたことにもそういう思いが込められています。われわれ個人を離れて会社の文化が育まれ、その文化がメンバーを通して、我々が接する/接しない一人ひとりが個々人として確かに生きていくための支えになったらどんなに良いか。
これからのきてんでは、中田さんの企画室と僕の会計室、二部屋合わせて10人くらい。中田さんとは今そういう規模感を目標にしています。それが今われわれにとって、自分と他人とで文化をお互いにこねていく上で想像できる丁度良さです。まあ正直どう転ぶか/どこまでできるか……わかりませんが、個々によって、個々を越えて、個々を助ける文化を作っていくことを、会社内における共同代表の責任だと考えて頑張っていきたいです。
会計室は「基点」をつくる
ところで、きてん企画室の “機転をきかせて起点をつくる” というタグラインを、かっこいいぜ、中田さんらしいね、と思っていましたが、僕がその代表になるのかと思うと、途端に自信がなく……。
さてどうしたものかと「きてん」を検索して見ると、「基点」という文字がでてきました。
1 距離や時間を計るとき、もとになる点や場所。
2 考えや行動のもととなるところ。
とのことでした。これだ、これです。
会計は、クリエイティブではありません。起点をつくることはありません。ちなみに「creative accounting」で検索すると、「粉飾決算」と出てきます。ダメです。
一方で会計は、事業の営みを四則演算しながら1と2は違うと説得力をもって伝えることができます。1を10にしたいのか、0にしたいのか、1は1のままでいいのか。指針は事業の数だけありますが、会計情報を基にして話の帳尻を皆でとっていくうちに、こうすると良い感じかも、と認識が整っていくことがあります。みな言うことが違うけど向いてる方向はなんか揃っている。会計だけのおかげとは思わないけれど、ときおり得られるそんな実感が楽しいから、この仕事をしている気もします。
人も社会も、本質的に完全な帳尻なんてとれっこない。整って見えるものの裏側では都度何かを取り込んだり、見ないことにしたりしながら、進んだり戻ったりしている。
個々の事業も、熱量や感情、取引とお金を含みながら右往左往している。それが面白いし、生きていると感じる。そんな中で、右往左往の基となる点の1つを、会計という立場で置けていったら。まだ見ぬ帳尻を、10に1つでも探ってもらうきっかけとなったらと思うんです。
会計自体がクリエイティブでなくて良い理由は、事業には過去の取引、そこに付随するお金や事務、それが起こる経緯が膨大に堆積していて、新しいものは必ずその経緯の堆積の中から生まれるからです。だから会計処理自体の8割が単発で見ると過去の繰り返しであっても、それが代替可能で効率化の対象であってもいいのです。それでも、クリエイティブが立ち止まったとき、必ずすぐそばに「会計」が立ちのぼります。そこで新たな「基」点を見つけて、また動き出す。そういう時間差の動静の連鎖をもしつくれたら、それはもうすでに創造と言っていいんじゃないか。
会計の8割は拾い仕事と整理仕事です。きてん会計室ではその繰り返しの中で、その事業に息づく文化をより風通し良く、かつ厚みを深めていくような仕事を志していきたいです。

Text by
五藤 真 (ごとう まこと)
事業のきてんをつくるバックオフィスカンパニー〈株式会社きてん〉の代表取締役社長/きてん会計室ディレクター/税理士。2025年9月、猫の手税理士事務所及び株式会社きてんに参画。